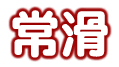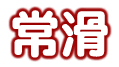|
登り窯
全長22mのこの窯は、1887年(明治20)に30人の窯仲間によって築かれました。傾斜地を利用して8つの室があり、最下部の焚き口で石炭を、第2室で松葉・薪を焚いて、熱が窯全体に行き渡るように造られています。窯入れから窯出しまでは約40日を要します。常滑で残る唯一の登り窯で、窯本体だけではなく周辺の作業場も保存されている点も貴重です。焚き口の前にある荷車は常滑焼の瓶がちょうど並べられる幅になっています。

登り窯
常滑市歴史民俗資料館
常滑焼の生産道具や中世から現代までの製品が展示されています。ビデオなどもあり、常滑焼に関する基本的な知識が得られます。
2.常滑湊跡
常滑警察署の東側に残る細い水路が常滑湊の跡です。1958年(昭和33)に新開町ができるまでは、県道252号のやや西側が海岸線でした。
3.旧道沿いの町並
常滑湊に接して、現在の栄町付近の旧道(県道252号)東側に常滑を代表する家が建ち並んでいました。現在でも、日本棋院常滑支部(瀧田商店・木綿問屋)、竹村仁平家などが残り、その雰囲気を伝えています。県道252号と海岸線との間は荷揚場・倉庫として利用されていました。北条海岸(現アーク証券の地点)にあった1828年(文政11)建立の常夜燈は、市民アリーナ近く(新開町3丁目)に移されています。県道252号の陶磁器会館西の交差点の北西には木造3階建の丸久旅館があります。1935年(昭和10)、宮大工によって建てられ、半円形を上下にずらした明窓や欄間の彫刻など、意匠のこらされた造作が見られます。
4.消防資料館
常滑市消防署の一角に消防資料館があります。常滑市内で使われていた竜吐水(木製ポンプ)・水鉄砲・まといなどの消防用具などが展示されています。

消防車
|